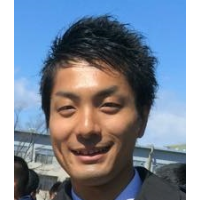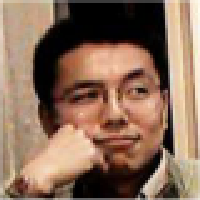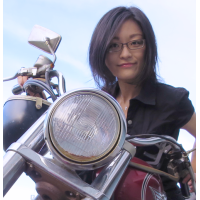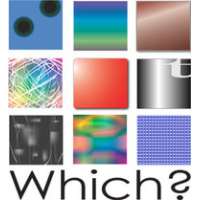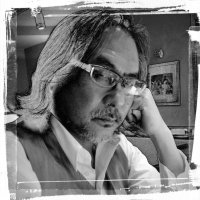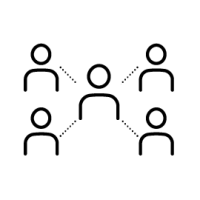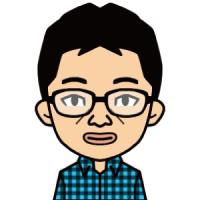【概要】
こども達が安心して暮らせる街作りの一環として、
近所、通学路付近の「こども110番の家」の位置情報やその付帯情報(店の営業時間など)を可視化するアイデア。
親子で近所を散歩しながらスマホを利用して上記情報を閲覧し、「こども110番の家」の場所を確認、そしていざという時の対応を親子で確認するためのツールとしての利用を想定。
【現状の課題】
1.全国的にこどもを狙った犯罪が増えている。
2.近所のどこに「こども110番の家」があるのか知る術がない。
①こどもも含め、近隣住民に聞いてみても
「聞いたことはあるが、どこにあるかは分からない」とのこと。
②Webで検索しても見つからない。
3.日頃から練習、シミュレーションでもしていない限り、
こどもはいざというときに「こども110番の家」のお店、住宅に逃げ込みづらい。
4.情報の更新頻度が低い
「こども110番の家」の看板のあるお店でその登録店舗の所在が
記されている地図(紙)を発見!しかし平成22年版だった。
以降、更新されていないとのこと。
※ご近所の「こども110番の家」のお店の方や、知り合いの小学校の先生、新潟市内で小学生ぐらいの子供を持つ親にヒアリングさせていただいた結果をもとにしています。
※2016/1/16時点、ヒアリング数はまだそんなに多くありません。市内/市外にかかわらず「うちの地域はこういう運用でうまく情報共有できてるよ」などの情報、ご意見等ありましたら是非ともいただければと思います。
【データセットに関するアイデア】
1.「こども110番の家」の位置情報のデータ化
2.登録形態は店舗、住宅など。店は店名までデータとして持つが、
住宅の場合は位置情報までとする(表札情報まではデータ化しない)。
3.店舗の場合は営業時間、定休日情報も持つ。
4.店舗の場合は、平均常駐店員数、防犯係有無、防犯カメラ有無など
最低限の防犯体制の情報もあるといい。
5.「こども110番の家」だけでなく、後述のセーフティーステーション
などの類似活動,施設も掲載。
【アプリに関するアイデア】
1.「こども110番の家」の位置情報をマップ上に表示
2.現在地から最寄りの「こども110番の家」までルート案内。
3.店舗の登録も多い(というかほとんど?)ので、営業時間もわかるように。
リアルタイムで営業時間中の「こども110番の家」を
検索できるようにする。
→逃げ込もうとしたら閉店してた!とならないように。
4.スタンプラリー機能などを持たせて、こどもが遊び感覚で楽しく
継続的に「こども110番の家」を確認できるように。
スタンプを貯めて、その達成率をクラス/学年対抗で競わせるなど。
(ibeaconを登録店舗、住宅に設置し、近くにまで行くとスタンプがたまるなど)
5.地域ごとの登録数、更新頻度の可視化。
住みやすい地域の一つの指標として。
【今後の展開(案)】
1.地域住民と「こども110番の家」の方とのコミュニケーションを増やし、
地域住民間の連携を深める。地域内の人と人のつながり(和)の醸成。
【備考】
1.「こども110番の家」はお店、住宅などの形態があります。
2.「こども110番の家」以外に、類似の活動があります。
(1)セーフティーステーション ...CVS (Convenience Store) の活動
※他にもあれば是非教えてください。